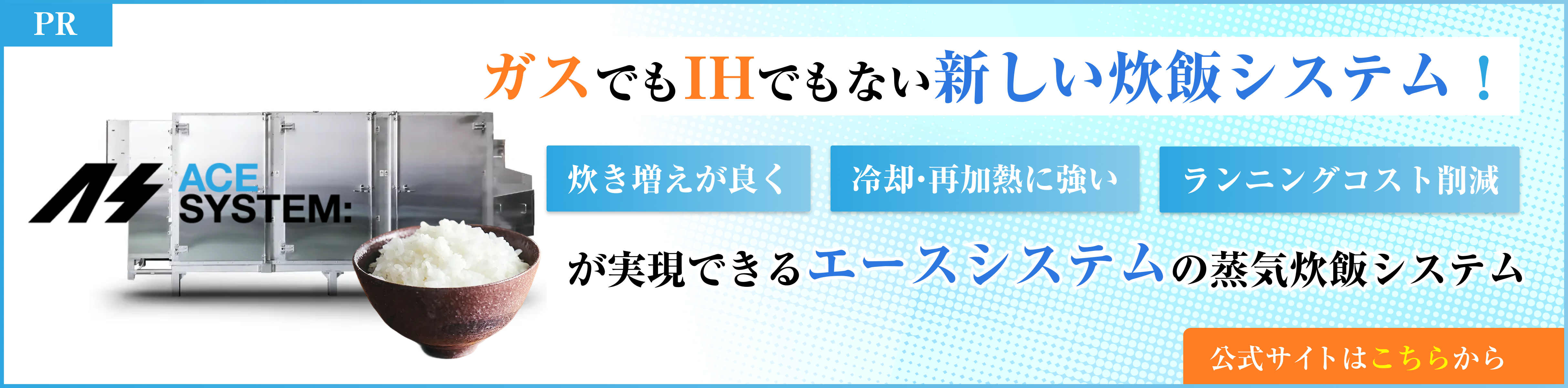厨房で使用する業務用機器の中で重要なのが、炊飯システムです。導入する業務用炊飯システムによって、ランニングコストや見栄え、味が変わります。
業務用炊飯システム選びに失敗すると、炊飯の効率や出来栄えが悪くなってしまう可能性が高いです。そこでこの記事では、業務用炊飯システムの種類や選び方について解説します。
業務用炊飯システムについて詳しく知るためにも、この記事をチェックしてみてください。
厨房で使用する業務用炊飯システムの種類
厨房で使用する業務用炊飯システムの種類は以下の3つです。
それぞれの炊飯方式を把握して、どの方式が厨房にあっているかをチェックしましょう。
蒸気炊飯
蒸気炊飯はお米を直接加熱するのではなく、蒸気で包み込むように加熱する方式です。蒸気炊飯の最大のメリットは、お米一粒一粒がふっくらと炊き上がる点です。
お米は、蒸気に包まれることで、芯までしっかりと熱が通り、粒立ちが良く、もちもちとした食感になります。また、お米の表面が焦げ付きにくいため、焦げ臭さがなく、ご飯本来の甘みを引き出せます。
蒸気炊飯は、大量調理に適しているという点も大きなメリットです。一度に大量の米を炊くことができ、短時間で炊き上げられます。
蒸気炊飯は飲食店や病院、学校などの大規模な施設で利用されています。
ガス炊飯
ガス炊飯は古くから親しまれてきた伝統的な方式です。ガス炊飯の特徴として、まず挙げられるのはその火力の強さです。
炎が直接釜底を加熱するため、短時間で一気に炊き上げられます。高温短時間の加熱は、お米の芯まで熱を通し、ふっくらと炊き上げるのに最適です。
また、ガス炊飯はシンプルな構造で、電気式やIH式と比較して構造が単純なため、故障しにくく、メンテナンスが容易です。初期費用は比較的安価であり、ランニングコストも抑えられる傾向にあります。
IH炊飯
IH炊飯とは、電磁誘導加熱を利用した炊飯方式です。釜自体が発熱するため、お米にムラなく熱が伝わり、ふっくらとした炊き上がりを実現します。
火を使わないため、安全性が高く、厨房の温度上昇を抑えることも可能です。業務用IH炊飯システムの大きな特徴の一つは、高い火力と温度制御の精度です。
短時間で大量のお米を炊き上げることができ、しかも一粒一粒が立った、ふっくらとしたご飯を炊き上げられます。また、IH炊飯は、省エネ効果も期待できます。熱効率が高いため、ガス炊飯システムに比べてエネルギー消費量を抑えられます。
また、保温機能も充実しており、長時間美味しくご飯を保温することが可能です。
厨房の業務用炊飯システムを新設・入替する際にチェックするポイント
厨房の業務用炊飯システムを新設・入替する際にチェックするポイントは以下の5つです。
それぞれのポイントを把握することで、業務用炊飯システム選びでの失敗を防げるでしょう。
炊き増え率
業務用炊飯システムの新設や入替を検討する際、炊飯量に直結する「炊き増え率」は、重要なポイントです。炊き増え率とは、炊飯システムに投入した米の量に対して、実際に炊き上がったご飯の量が増える割合のことを指します。
炊き増え率が高いということは、少ない米で多くのご飯を炊き上げることができるため、食材費の削減につながります。
ただし、しかし、炊き増え率ばかりを重視すると、ご飯の品質が低下してしまう可能性もあります。炊き増え率が高い炊飯システムの中には、ご飯がパサついたり、べちゃついたりするものもあるからです。
炊き増え率が高く、かつ、ふっくらと炊き上がる美味しいご飯を作れる炊飯システムを選びましょう。
導入コスト
業務用炊飯システムを導入する際は、導入コストも必ずチェックしましょう。導入コストは、初期費用とランニングコストに大きく分かれます。
初期費用は、炊飯システム本体の購入費用はもちろん、設置工事費や配線工事費なども含まれます。機種によっては、オプション機能や付属品も必要になる場合があり、総額は想定以上に膨らむ可能性もあるため注意が必要です。
一方、ランニングコストは、電気代やガス代といったエネルギーコストに加え、メンテナンス費用や消耗品費などが挙げられます。
炊飯システムの導入コストを把握するためには、複数の業者から見積もりを取ることが重要です。見積もり内容を比較することで、各社の価格設定やサービス内容の違いを把握できます。
また、導入後のランニングコストについても、各社で差異があるため、詳細な説明を求めましょう。
炊飯方式
炊飯方式は、炊き上がりのお米の品質や厨房の効率化に大きく影響するため、特に注意すべきポイントです。炊飯方式は、大きく分けてガス式、蒸気式、IH式などがあります。
それぞれの方式にはメリット・デメリットがあり、どの方式を選ぶかはお店や施設の規模やメニュー、予算などによって異なります。たとえば、大規模な施設では、一度に大量のご飯を炊けるガス式や蒸気式が適しているかもしれません。
一方、小さい飲食店では火加減の調整が自動でおこなわれるIH式が向いているケースが多いです。厨房に適している炊飯方式を選んでみてください。
サポート体制
業務用炊飯システムの新設や入替を検討されている飲食店様にとって、機器の性能はもちろん、導入後のサポート体制も重要な判断材料です。
サポート体制が充実していると、万が一の故障やトラブル発生時、迅速かつ適切な対応が期待できます。たとえば、緊急時の修理対応や操作方法に関する問い合わせ対応、定期的なメンテナンスなど、さまざまな場面でサポート体制の充実が活かされます。
た、導入前の段階から、専門スタッフによる機器選定のアドバイスや、設置場所の設計、操作方法の研修など、きめ細やかなサポートを受けることが可能です。導入後のトラブルを未然に防ぎ、円滑な業務開始をサポートしてくれます。
導入機器のサイズ
厨房炊飯システムを導入する際は、導入機器のサイズもチェックしましょう。
大きすぎる炊飯システムを選んでしまうと、設置スペースが不足したり、調理動線が妨げられたりする可能性があります。逆に、小さすぎる炊飯システムを選んでしまうと、頻繁に炊飯する必要が生じ、作業効率が低下してしまうかもしれません。
また、炊飯システムの高さも重要な要素です。背の高い炊飯システムは、上部の操作パネルが見えにくかったり、清掃がしにくかったりする可能性があります。一方、低い炊飯システムは、作業スペースが狭くなる可能性が高いです。
炊飯システムのサイズ選びは、一見かんたんに思えますが、さまざまな要素を考慮する必要があります。最適なサイズを選ぶためには、厨房の設計図や実際に厨房で働くスタッフの意見などを参考にしながら、慎重に検討することが大切です。
厨房に業務用の炊飯システムを導入するならエースシステム株式会社がおすすめ

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | エースシステム株式会社 |
| 所在地 | 大阪府和泉市あゆみ野3-1-3 |
| 創業年数 | 1988年創業 |
| 商品名 | スチームライスマシーン |
| 公式サイト | https://www.acesystem.co.jp/index.html |
厨房に業務用の炊飯システムを導入するならエースシステム株式会社がおすすめです。エースシステム株式会社には以下3つの特徴があります。
それぞれの特徴を把握することで、エースシステム株式会社の魅力がわかるでしょう。
炊き増え率が高くランニングコストを削減できる
エースシステム株式会社の業務用炊飯システムは、炊き増え率が高くランニングコストを削減できます。お米の高騰が進む中、エースシステムの装置では炊き増え率が約2.3倍〜2.5倍と高く、釜炊飯の2.15倍と比較しても優れた調整が可能です。
炊き増え率が向上することで、原料となる白米の使用量を削減でき、コスト削減に貢献します。
素材の良さをひきだす蒸気炊飯
エースシステム株式会社が開発した蒸気炊飯は、素材の持つ本来の味を最大限に引き出せると評判です。過熱水蒸気を熱源とする独自の炊飯方式で炊き上げるため、高温の蒸気が米粒一つひとつを包み込むことで、短時間で芯までしっかりと加熱されます。
急速な加熱により、米の酵素の働きが抑えられ、パサつきやベタつきを抑えた、ふっくらとした炊き上がりを実現するのがポイントです。また、高温の蒸気は殺菌効果も高いため、より安全なご飯を炊き上げられます。
大阪公立大学と産学提携の信頼性
エースシステム株式会社は大阪公立大学との産学連携をして、共同開発をしています。連携を通じて、それぞれの強みを活かし、新たな価値を創造しているのがポイントです。
大阪公立大学で生まれた最新の食品加工技術を、エースシステム株式会社が実用化することで、より効率的で安全な食品加工を実現しています。また、エースシステム株式会社の現場での知見を、大阪公立大学の研究に活かすことで、より実用的な研究成果を生み出しているのも特徴です。
共同研究して開発したシステムは特許を取得しています。
まとめ
業務用の厨房機器で重要な炊飯システムの炊飯方式は、蒸気式とガス式、IH式の3種類があります。それぞれメリット・デメリットがあるため、厨房にあった炊飯方式を選ぶことが重要です。
炊飯システム選びをする際は、炊き増え率や導入コスト、サポート体制などもチェックしましょう。この記事を参考にして、厨房に最適な業務用炊飯システムを導入してみてください。